労災保険と民事損害賠償の関係
今や私たちの誰もがリスクに備え何らかの保険に入っている。会社も労働災害に備え労災保険に加入していると理解している方も多いだろう。労働基準法は労働災害が起きた場合は、たとえ会社に過失がなくても被災労働者に補償を行うことを義務づけている。
そしてこの補償義務は、労災保険による給付が行われることにより免除され(労働基準法 第84条1項)、同一の事由については、民法による損害賠償の責めを免れるとされている(同84条2項)。だが実際には会社に対し、不法行為や安全配慮義務違反という債務不履行により、損害賠償を要求する事態が起きている。これは一体どうしてなのだろう。
その理由は、労働基準法の84条2項が定める「同一の事由」という文言の解釈にある。最高裁は「同一の事由」とは単に同一の事故から生じた損害ではないとし、労災保険給付の趣旨目的と損害賠償の対象となる損害とが同じ性質であり、補完性を有する関係にある場合を言うとしている。
そして労災保険と同一の事由に当たるのは、財産的損害のうち「消極損害」(主として逸失利益)のみであって、「積極損害」(実際に支出された入院費や付添看護費、葬儀費、弁護士費用など)や「精神的損害」(慰謝料)は同じ性質であるとは言えないと結論づけている(青木鉛鉄事件 昭和62年7月10日)。また別の事件では労災保険の特別支給金についても、保険給付のように損害を填補する性質を有しないため、損害賠償から控除することはできないとしている。
つまり労災保険の給付により会社が損害賠償責任を免れるのは、「消極損害」である逸失利益=労働者が被災していなければ得られたはずの利益で、主として給与収入相当部分だけということになる。このため、「積極損害」や「精神的損害」は損害賠償を要求されることになる。
例えば被災労働者が被った全損害が70万円で、内訳は逸失利益が50万円、慰謝料が20万円だったとする。この時、労災保険から80万円が支給されると、全損害の70万円は労災保険でカバーされているが、会社が免責になるのは「同一の事由」の逸失利益分の50万円だけで、慰謝料部分の20万円については損害賠償責任を問われることになる。
もちろん実際に会社が賠償金を支払うのは、裁判で被災労働者側の主張が認められた場合に限られる。業務災害について、会社側の故意や過失、安全配慮義務違反を立証する責任は被災労働者側にある。
労災保険が年金の場合の取扱い
労災保険と民事損害賠償の関係で問題になるのは、労災保険の給付には一時金だけでなく、年金もあることだ。労災保険の給付が一時金であれば、民事損害賠償金との調整は容易に計算できるが、年金による給付になると、労災保険の金額をいくらとして扱えばよいかが問題になる。現時点で支給された分だけが調整の対象になれば、民事損害賠償額から控除される額が少なくなり、会社の負担は重くなる。逆に将来に渡って支給される分までが控除できれば、会社の負担は軽くなる。
この問題について最高裁は昭和52年に2つの事件で相次いで、年金による労災保険の将来給付分は民事損害賠償額から控除できないとする判断を示した。これに対し法律の専門家や会社関係者からは、被災労働者が労災保険と民事損害賠償金を2重に受け取ることになり公正さに欠けるとか、強制加入の上、全額会社負担で保険料を払っている会社の保険利益が損なわれるという意見が相次いだ。
このため厚生労働省は、昭和55年に労災保険法の改正を行い、労災保険の年金給付が行われる場合、会社は前払一時金の最高限度額まで民事損害賠償が免除されるという規定が設けられた(労災保険法・附則64条1項)。前払一時金とは、労災保険の障害補償給付と遺族補償給付に設けられている仕組みで、被災労働者やその遺族が一時的に多額の保険金を必要とする場合に備え、年金の一部を前払いで受け取れるようにするものだ。この改正により現在は、被災労働者またはその家族が前払一時金を請求しなくても、会社は前払一時金の最高金額分までは民事損害賠償責任が免責されることになっている。
一方、被災労働者は労災保険の給付と民事上の損害賠償金の両方を受け取れるとは限らない。労災保険法は附則の64条2項で、「同一の事由」について保険給付に相当する民事損害賠償が行われた場合には、政府はその金額相当分の労災保険の給付を行わないことができると定めている。
例えば会社が民間の保険会社と契約した上で、事故が起きた場合には保険会社からの保険金を被災労働者に支払うことがある。こうした場合、会社からの保険金が逸失利益に相当する場合、その保険金額に相当する額の労災保険の給付は行われない。
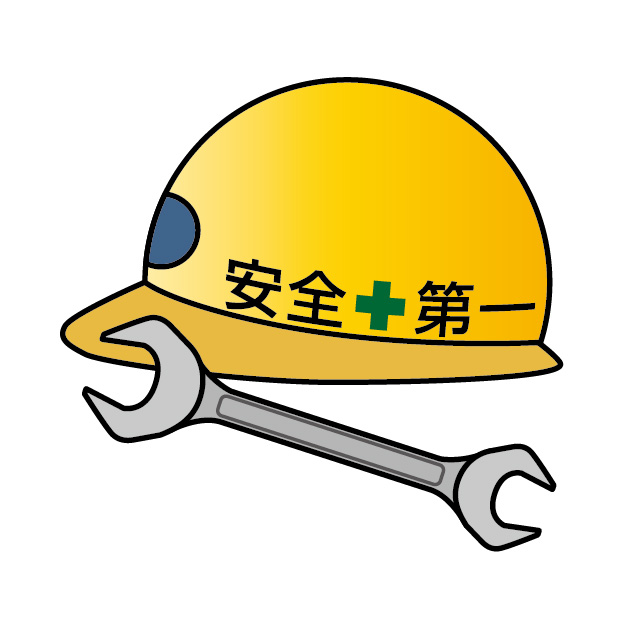
第三者行為災害の場合の調整
労災保険事故には、会社と雇用されている労働者以外の第三者が原因となって起こる 第三者行為災害 がある。仕事中の交通事故や建設業、構内下請けのように自社が管理する区域・施設内で他社の労働者が事故に合うケースなどが第三者行為災害になる。
この場合、被災労働者は第三者に対し損害賠償請求することになるが、労災保険からの給付が行われると、労災保険が支給した金額分の損害賠償請求権は保険者である国が代位取得する。そして保険給付が行われるごとに、国が第三者に対し損害賠償を請求するという求償が行われる。逆に第三者が先に「同一の事由」について損害賠償を行うと、国は第三者が行った損害賠償の金額分の労災保険の給付を行わない。
この第三者行為災害には、第三者が思わぬ高額の損害賠償責任を負う法律上の落とし穴がある。先に述べたように会社が雇用する労働者が労災保険の年金給付を受けることができる場合は、会社の損賠賠償責任は将来に渡って支給される年金給付の内、前払一時金の最高限度額分までは免責になる。しかし第三者行為災害にはこうした免責の規定がないため、高額の賠償金の支払いが命じられる可能性がある。そして第三者になるのは会社とは限らず、私たち個人やその家族が些細な事故や不注意で行為者になることもある。
損賠賠償額は過失相殺によっても調整されることがある。事故が起きた原因について、被災労働者にも一定割合で責任があると認定されると、過失相殺が行われ損害賠償額が調整される。この過失相殺は会社に有利な方法で行われる。
仮に全損害が100万円で、労災保険から40万円の給付があったとする。そして過失割合は労働者側が30%で、会社側が70%と認定されたとする。この時、会社の損害賠償額は、全損害の100万円の70%=70万円から、労災保険から支給された40万円を差し引いた残りの30万円になる。つまり会社の損害賠償は労災保険の給付によってカバーされる格好になる。
被災労働者から見れば、自分が被った被害100万円のうち、労災保険の40万円でカバーされていない60万円について、会社側に責任が70%あり、42万円が損害賠償額になると考えてしまうが、裁判所はこの計算は認めていない。
そして会社員が労災事故に合うと、厚生年金保険から障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されることがある。この場合は厚生年金保険が全額支給され、労災保険は一定の割合で減額される。
労災保険も民間の保険と同じように万全とは言えない面があるため、会社も個人も自助努力による備えが必要だ。
2017/4/23
事務所新聞のヘッドラインへ
オフィス ジャスト アイのトップページへ





