女性管理職が経営を左右する事情とは
現在、政府は働く女性を増やそうと躍起になっている。経済成長のために必要な労働力は、労働者の人数と労働時間、そして労働生産性で決まってくる。長期的に人口が減少するため労働者の数は減り、労働時間は法的規制があるためこれ以上増やせない。
となれば、労働生産性を上げると同時に、働く女性を少しでも増やし、それも短時間のパートではなく正社員として長い時間働いてもらうしかない。女性活躍推進法で、大企業に対し女性管理職の割合を公表することを求めるのも、こうした事情がある。
女性管理職の実態調査
では、現在、女性管理職の割合はどのくらいなのだろう。人事の専門誌である「労政時報」が、厚生労働省の「賃金構造基本統計」を基に管理職構成の実態を調査、公表している。それによると、従業員100人以上の企業における女性管理職の割合は、2013年で約10%になっている。2003年の3.2%、2008年の9.1%から着実に増加している。(調査結果の概要はこちら・PDF)
女性管理職の中身を詳しく見ると、部長は0.1%で増減なし、課長、係長では0.2~0.3%の増加に留まっている。そして「その他の役職」が年を追うごとに大幅に増加している(2.4%→7.9%→9.0%)。この背景としては、ここ数年、部や課といった組織ではなく、チームやグループ、プロジェクトといった組織単位による業務遂行が増えていることが挙げられる。
業種別に見た男性・女性の役職者の割合で、女性比率が最も高いのは「医療・福祉系」で、男女の役職者比率は男52%、女48%、次が「教育・学習支援業」で、男80%、女20%となっている。男女比で女性役職者の比率が最も低い業種は建設業(2.5%)で、次いで「運輸・郵便業」(4.2%)と続く。
立ちはだかる心の壁
では、政府の目論み通り女性管理職は増やすことができるだろうか。女性管理職を増やすには4つの階段があり、企業はこの階段を1段ずつ登る必要がある。
最初の階段は均等待遇の実現で、その次がワーク・ライフ・バランスの実現、そして、女性労働者の活性化・基幹戦力化と進み、最後が管理職候補者数の確保・維持と進む。一足飛びに階段を上がるのは難しいため、自ずと時間がかかる。また、管理職の育成は男女を問わず人材育成に関する事項となるため、この面でも息の長い取り組みが求められる。
そして、女性管理職の登用に大きな壁となるのは、当事者である女性社員と経営陣・男性管理職、両者に存在する「心」の問題だ。男女雇用均等法が施行され20年が経過し、男女間の差別的取り扱いの解消は進んだが、この間、女性社員は自分が管理職となるキャリアを想定してこなかった。そのため、教育や自己啓発、挑戦機会の付与といった点で十分な蓄積や経験がなく、管理職となることに躊躇することが珍しくない。また、管理職になると社内の女性グループとは溝が出来るし、男性管理職のグループにも入れず、孤立を懸念する傾向もある。
一方、経営陣は女性管理職を増やそうという声に対しては、「なぜ」という素朴な疑問がある。女性管理職を増やしても業績向上につながる確かな見込みもないし、顧客は法人なので男も女も関係ない。せいぜい採用時のイメージアップに寄与することぐらいしか思い浮かばない。逆に施策の導入によるコストアップや、辞めなくなった女性社員の処遇に見合うだけの仕事、職務が用意できるのかという不安もある。
男性管理職は女性管理職候補となる部下を増やしてくれという要請には、ホンネでは面倒で厄介な話と受け止めていることが多い。男性の部下を育成するだけでも難しい課題なのに、女性社員を育成するのは気も使うし、制約もある。そもそも女性社員は組織内の肩書きよりも実際の待遇を重視するため、管理職に昇進・昇格するというインセンティブが効かない。一歩間違うとセクハラやパワハラとなりかねないリスクもある。こうした経営陣や男性管理職の心の壁を取り除くのは容易ではない。時間をかけて徐々に認識を改め、理解を深めてもらうしかなさそうだが、そんな悠長に構えていられない事情もある。

経営の基本が揺らぐ事態の到来
女性社員や女性管理職の活用について悠長に構えていられない事情とは、経営についてのこれまでの基本や原則が揺らいでいるためだ。長きに渡って経営の基本とされてきたのは、業界内で何らかの方法により差別化を図り、競争優位な状態を作り出し、これを維持・発展・強化させることで収益に結び付けるというものだった。
こうした考え方に疑問符が突きつけられているという主張を唱え、新しい対策を提案し注目を集めているのがアメリカ・コロンビア大学ビジネススクールのリタ・マグレイス教授だ。教授によれば、経営陣は自社にとっての最大の脅威は業界内の競争にあるという考え方から抜け出し、「持続する競争優位」という概念を捨て、「一時的な競争優位」に基づいて経営する必要性を説いている。

Rita McGrath
不確実で不安定な経営環境における戦略の権威として高い評価を得ている。経営に関する世界的な賞とされる「Thinkers50」によって「経営思想において最も影響力のある20人」「ツイッターでフォローすべきビジネススクール教授の10人」に選出。
業界内での競争優位が持続しないという事例は枚挙に暇がない。デジカメの普及により写真フィルムにこだわって経営破綻したコダック、スマホによって携帯電話事業の売却に追い込まれたノキア、音楽配信サービスによって主役の座を明け渡したソニーのウォークマンなど、いずれも業界の外からの脅威により競争優位が持続しなくなった例だ。こうした世界的規模の話だけなく、中小企業でも業界の外で起きた技術革新や新しいサービスにより、従来の取引・商慣行が激変した例は数多くある。自社に直接関係なくても取引先の影響を被ることもある。
業界内の競争優位は長続きしないという前提に立てば、企業経営には一時的な優位性から別の優位性に乗り換えていく柔軟性が求められる。具体的には次のような経営姿勢が肝要になる。
- 既存の事業からの早めの撤退
- 収益事業から新規事業への経営資源の移転
- 失敗を避けるのではなく、失敗から学ぶ
- 計画はやり遂げるのでなく、気軽に見直す
- 変わり者によるイノベーションではなく、自発的にイノベーションが起きる体質にする
- アイデアを組織に合わせるのではなく、アイデアを活かすために組織を変える
- 分析よりも実験を重視し、「異見」を尊重する
これらを実現にするには、情報収集や意思決定に関わる人たちの多様性が求められる。男性・正社員・新卒採用者が中心の組織ではなく、女性、中途採用組、社外取締役、外部の専門家集団といった異質な集団を組織の中核に抱え込む必要がある。
私たちの働き方も変わる
企業が「一時的な競争優位」という考え方に基づく経営方針に転換すれば、そこで働く社員の働き方も変化を迫られる。マグレイス教授によれば、企業で働く人はキャリアは一直線(=現在の延長線上に将来がある)という考えを捨て、「変動」が標準になるとしている。
企業が次々にやって来る優位性の波に乗るのに役立つスキルや能力を備えている社員は厚遇される。そのため、会社の行う教育研修だけでなく、自己投資によりスキルを磨き、必要とされる存在であり続け、時には他社に自分を売り込むだけの価値を提供できるように備えておく必要がある。教授の考えを記した「競争優位の終焉」には、働く個人が一時的な競争優位の経営に対応できるかがわかる自己評価テストと、それに基づく対策が示されている。
『自己評価テスト』(以下の質問にはい・いいえで答える。「いいえ」が5つ以上なら、即行動)
- 今の会社を解雇されても、比較的簡単に同等の報酬で別の会社に同じような職を見つけることができる
- 今日、職を失っても準備は十分できており、次に何をなすべきかすぐにわかる
- 過去2年以内に、5つ以上の組織で有用な役割を担って働いたことがある
- 過去2年間に、業務に関係あるかないかに関わらず、以前は持っていなかった有用な新しいスキルを身につけた
- 過去2年間に、直接あるいはインターネットを通じて、講座や研修に参加したことがある
- 新たなチャンスをもたらしてくれそうな人の名前を最低10人は挙げられる
- 仕事またはプライベートの2つ以上のネットワークに積極的に関わっている
- 新たなチャンスに出合うために、時間を取り再訓練を受けたり、少ない給料で働いたり、ボランティア活動に従事したりできる資源(例:少ないローン、預貯金、配偶者の支援など)がある
- 給与以外に複数の収入源がある
- 新たなチャンスを見つけるための引っ越しや移動を厭わない
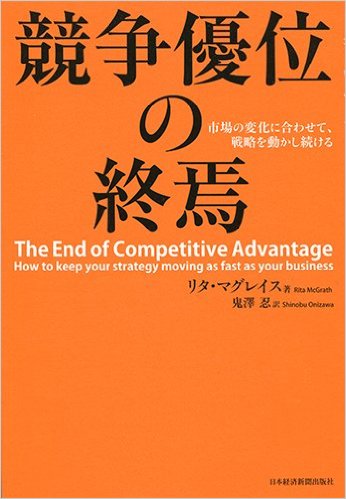
競争優位の終焉
マグレイス教授によれば、安心と安定が失われることは不安をもたらし、マイナス面や社会的なコストも上昇するが、その一方で、企業も個人を大きなチャンスに恵まれるとする。企業は成長の機会に恵まれ、個人はキャリアのつなぎ方も多様になり、起業する余地も広がる。一旦、働くことをやめた人にも活躍の場が提供され、一時的競争優位の経済で活躍するためのスキルや教育を得ることが可能になる。
2015/10/21
事務所新聞のヘッドラインへ
オフィス ジャスト アイのトップページへ





